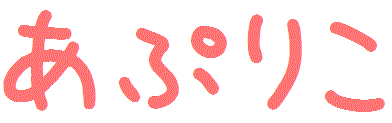都野津地域の現況
人口・世帯の状況
2025年1月20日現在・行政区
人口:2,994人
※人口(人)外国人世帯も含む(41)
-
【男性】1,412人
-
【女性】1,582人
65歳以上人口:901人
高齢化率:30.09%
世帯数:1,458世帯
-
【世帯当たりの人数】2.10人
自治会加入率:74.83%
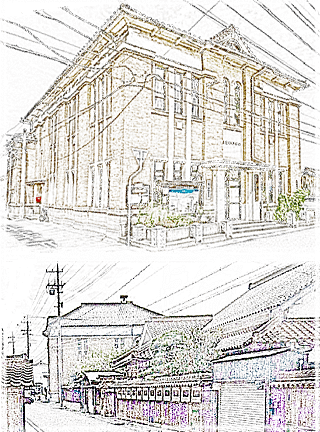
地域の特色
景観・歴史・文化・伝統行事など
都野津町は、江津市の西部に位置し、北は美しい日本海の海岸線と南に白砂の「はんだが浜」、西には桜並木の水尻川、東は漁業に生計を立てた先人たちが沖を眺めた「遠見が丘」に挟まれた落ち着いた街並みを有する。
現在の都野津町は、大昔海の底だったが、海岸がだんだん沖に行き砂浜が形成され人が住むようになった。砂浜だから田で稲が作れず、畑作が中心であった。また、砂浜海岸であるがゆえに地引網漁が産業の大きな一つでもあり、海砂からとられる砂鉄を山間部のたたら地域に持ち込み生計を立てている者もいた。近代になって、豊富な陶土(都野津層)を使って窯業の瓦産業が発達してきた。10数社の窯(登り窯)があり、西日本でも有数の瓦産業地となった。
しかし、近年瓦の販売が減少し、窯業が衰退し現在では2社ほどになっている。さらに生活手段として行商があり、その中でも反物行商、魚行商が盛んに行われた。魚行商は、浜田市の旭町都川から桜江町市山あたりまで、反物行商は、もっと広範囲で中国山地の大朝方面まで行っていたようだ。この行商によって、秋には物々交換で都野津には無い米を手に入れていたようだ。
このように、外に出ていくことが多い都野津町には、土着の文化や特別な伝統行事が少ない。秋祭りやとんど焼きといった伝統行事、町民運動会・文化祭・敬老会といった行事は地区民挙げて継承している。
地域文化遺産として、先代の佐々木凖三郎氏が残した「都野津会館」をはじめ数多くの建物遺産存在している。都野津会館は、国の登録有形文化財にも答申された。令和1年凖三郎を語る会において、「佐々木凖三郎記念館」という名称を追加命名した。また、家並みも瓦産業の発祥地として、当時の面影が各所に遺構されている。都野津駅は、大正9年12月25に開業され令和2年12月25日には、江津駅とともに100周年記念式典並びに記念行事が催された。
令和3年、つのづエントランス事業が動き出し、角の会・新四国八十八ヶ所・町づくり景観とつながり研究会が合同で事業を進める。令和4年度より、つながりづくりのキーパーソンとなる人材を育成する事業を始める。「笑みサポーター」は、つのみやっこ広場・あったかカフェでの活躍の場。そして、それぞれの町内で自治会長並びに民生児童委員の補助的なお手伝いができる人材として活動。育成事業として笑みサポーター養成講座を隔月で開催。
令和5年度終了間際より津宮小学校コミュニティスクールがスタート、令和6年度が本格的スタートとなる。地域のつながりを考える町づくりは、地域の子どもを鎹に広く世代間の交流を図っていく、そのためにコミュニティスクールは大きく寄与するものと確信する。町づくり計画の終盤を迎えて迎えている、残り2年は以降持続可能な地域づくりを進める為、担い手探し・担い手育成にも考慮する。



都野津町づくり協議会
活 動 目 標
生活の場・子育ての場である都野津町で、誰もが安心して住み続けることができる町づくりを目指します。
目的を達成するため、次の事業を行います。
1.広報活動を活発に行い、江津市末端行政への協力と町民相互の親睦事業の推進に関すること。
2.健康増進とスポーツ活動の推進に関すること。
3.町民同士の触れ合い福祉活動の推進に関すること。
4.安全・安心、快適な町づくりに関すること。
5.生涯学習の充実と伝統行事の継承など、文化の町づくりに関すること。
6.地域資源の有効活用及び開発などの地域おこし推進に関すること。